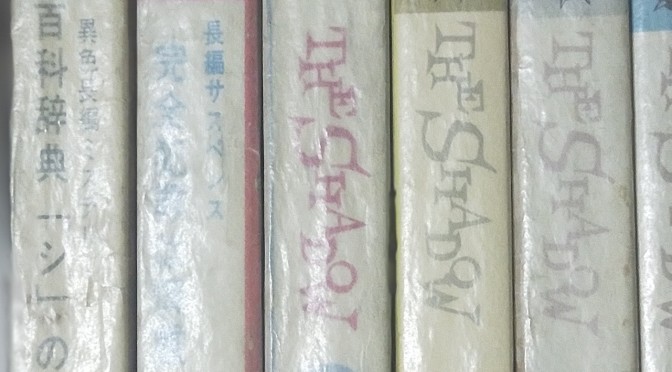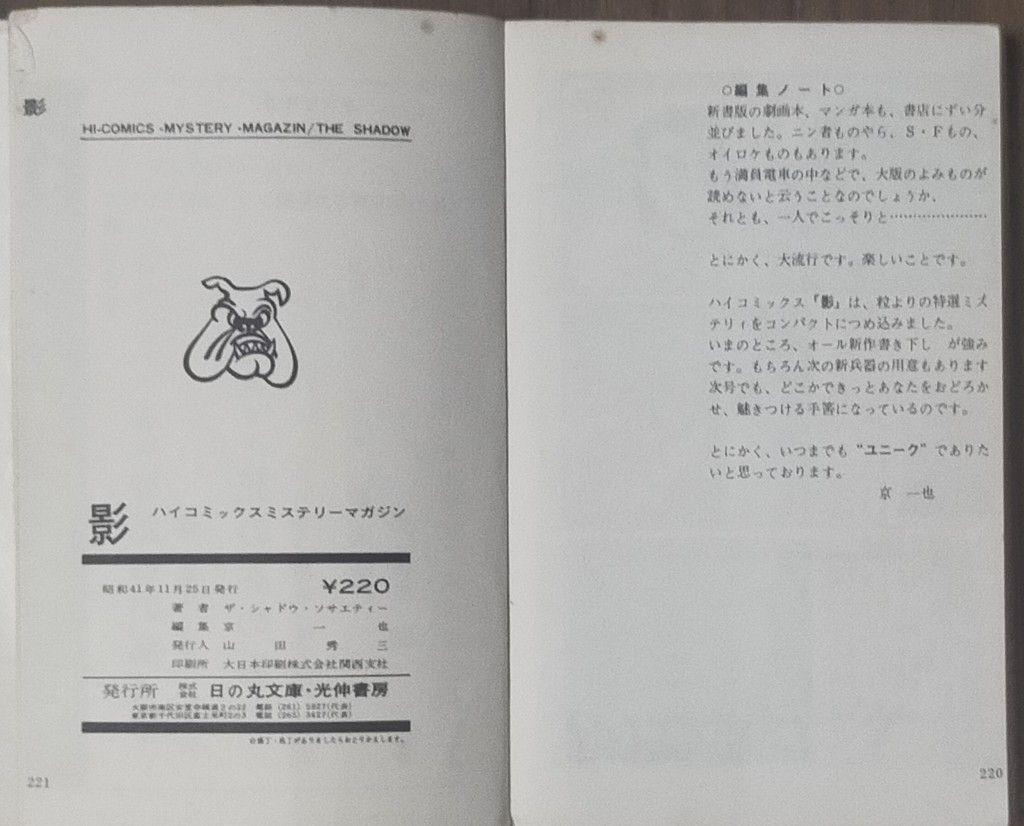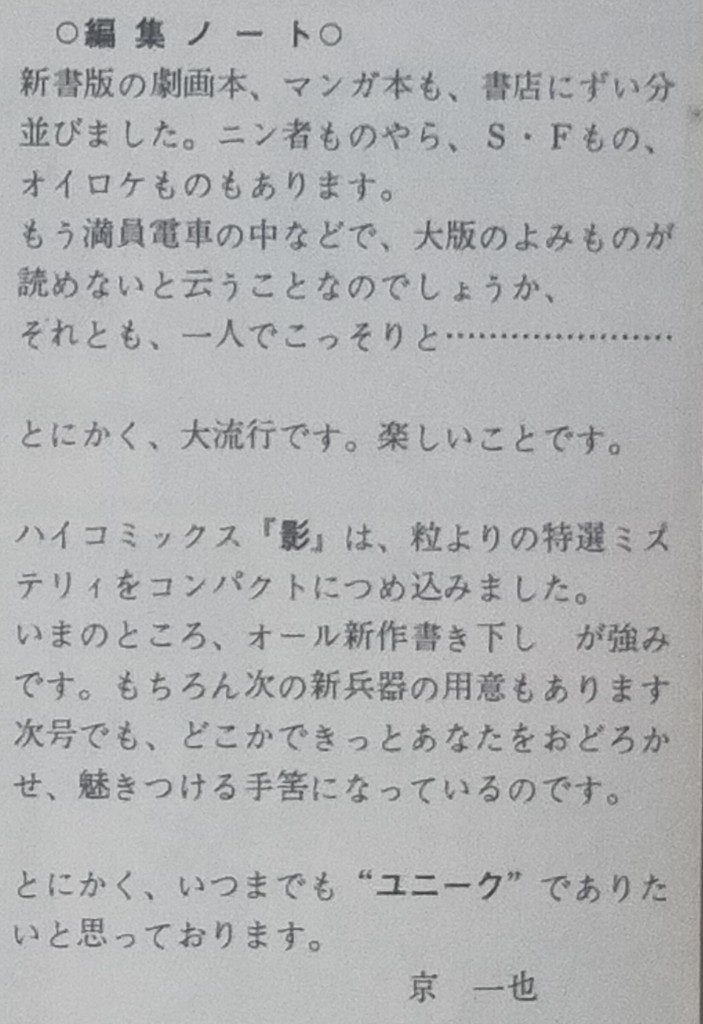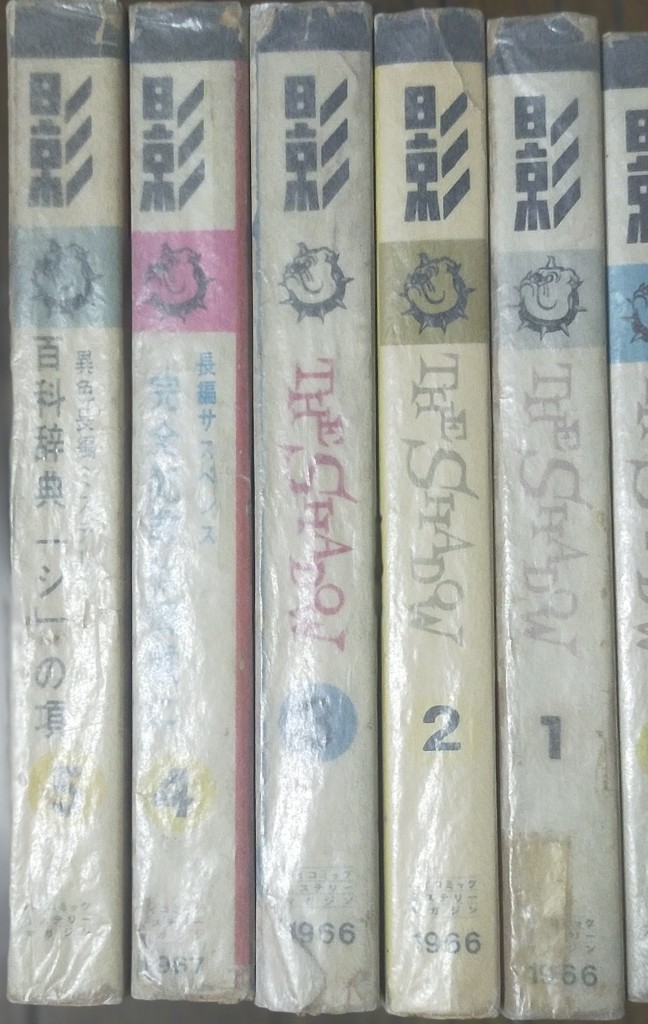石川フミヤス氏(1937〜2014)は劇画工房の一員であり、長きに亘りさいとうプロの作画スタッフとして活躍した。世間的な知名度こそ高くは無いだろうが、半世紀に及ぼうというマンガ制作者としてのキャリアを一言で言えば「職人」となろうか?
ほんの少しではあるが、石川フミヤスの貸本マンガ時代の作品を読んだが、創作にかける誠実な思いが伝わってくる作品が少なくない。商業的な成功とはまた、別問題なのであるが、商品としてのクオリティを長期間持続させることの難しさを思い知らされます。
今後、どれだけの石川フミヤス作品を読む機会に恵まれるだろうか?
2025.9.26記す。